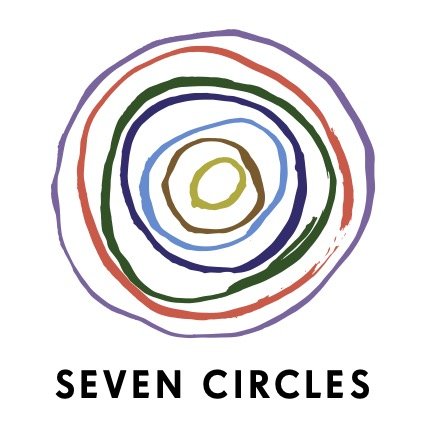アシテジという、子どものための舞台芸術の国際連合的組織がある。
子どもの健康的育成を演劇やダンスなどの舞台から全面に支えていきたいアーティストや演出家、演劇関係者から成り立っているインターナショナルな組織である。
その組織が開催している世界大会が、実は今、日本の東京で行われていて、未来フェスティバルという名前で色々な催し物を提供している。オンラインでオンデマンドで舞台を見ることができたり、関係者のための勉強会であったり、世界大会というだけあって、かなりのボリュームで持ってプログラムが組まれている。
https://assitejonline.org/?lang=ja
コロナの影響で対面でできないけれど、移動しなくて良いだけあって、沢山の参加者が各大陸から参加している。こういう大会に参加すると、世界は本当に縮まっている、と感じる。
各国で抱えている子どもを取り巻く問題や、その文化ならではだから出てくる舞台表現など、それぞれの視点から語り合ったり、意見を言い合ったり、解決策を見つけて行ったりする。
子どもが舞台芸術を経験する、ということは、虚構の世界の中で概念や感情を揺るがされたり、想像力を刺激して普段味わえないような世界観や別世界に行くことができる。また、今ある現実を形を変えて突きつけられ、考えさせられる機会であったり、もしくは子どもの存在価値をあるがままに認めてあげることにも繋がる。舞台芸術にはそんな力が秘していると思う。
例えばオーストラリアの作品で、「This is Grayson」(こちらはグレイソンである)という作品がある。
http://www.goldsatino.com/this-is-grayson
この作品はジェンダーやクィアーのアイデンティティを取り扱った作品で、男女という二局のカテゴリーに所属せずに、その間にいる人たちの生き方や思いを綴ったパフォーマンス。伝統的に社会が作り上げてきた型にハマらない人たちが存在することを舞台芸術で示すことで、このような思いを持ちながら、でも打ち明けられなかったり相談できない今を生きる子どもたちに存在価値を伝える大切な作品である。
この未来フェスティバルのスローガン。”未知なるものへ、旅のはじまり。子ども、文化。それが私たちの未来”
子どもたちを取り巻く文化の豊かさを改めて考え直し、まだまだアーティストとして出来ることを考えさせられた十日間でした。